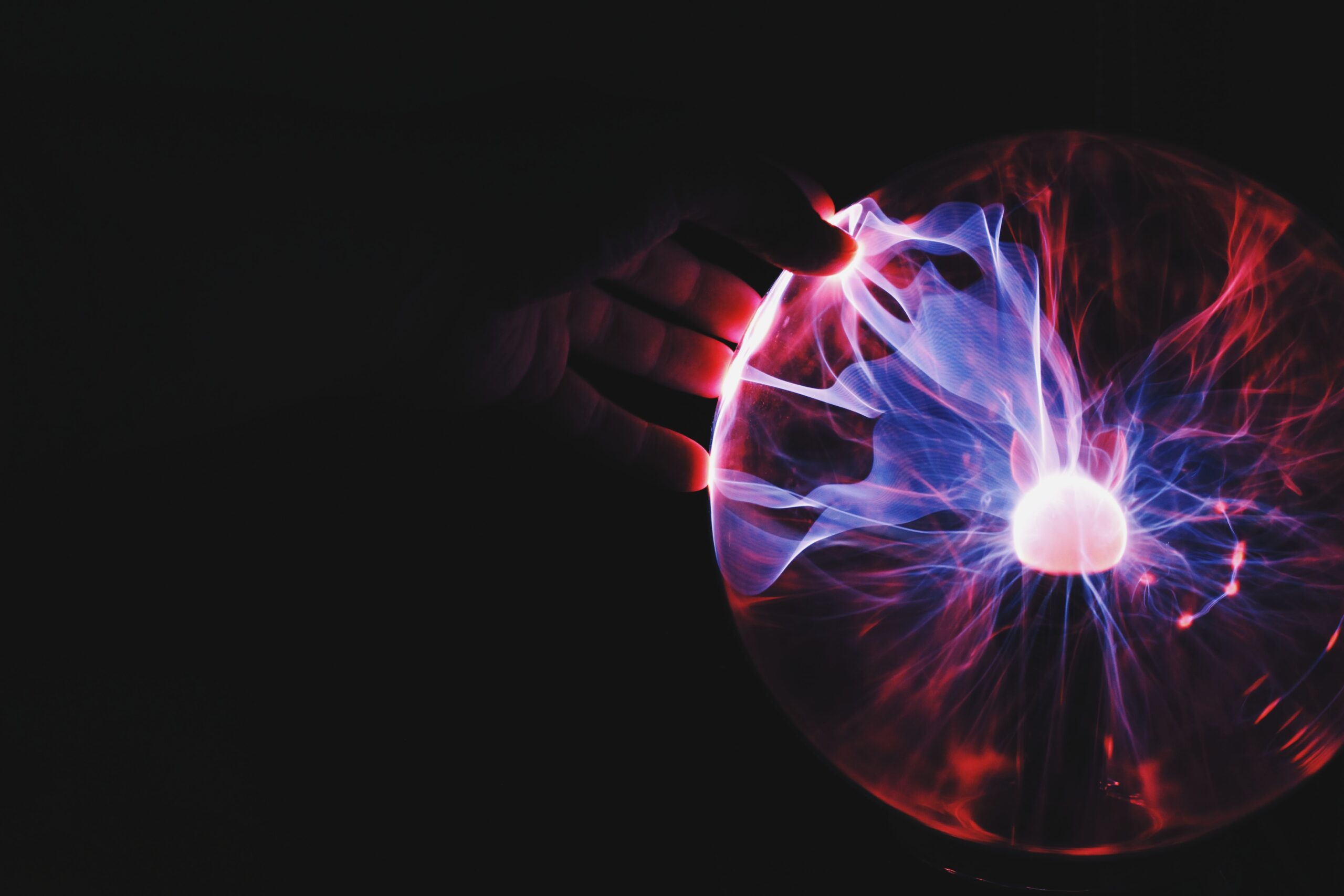今回は、「LEDと白熱電球の違い」についての説明です。
1.初めに
LEDについて簡単にまとめると、以下のようになります。
pn接合ダイオードに順方向電流を流すと空乏層付近に余分なエネルギーが発生するので、その余剰エネルギーを光エネルギーに変換して発光している部品。
そんなLEDですが、昨今ではLED電球という電球に置き換わる種類も登場していて、普通に家庭で使用できるレベルになっています。
その辺に普通に売っていますからね。

寧ろ積極的にLEDを使用するようになっていますが、何故白熱電球がLEDに置き換わっていく流れになっているのか考えたことがありますでしょうか?
単純に考えれば、LEDに置き換えるメリットが存在するはずですよね。
ということで、今回はLEDと白熱電球の違いについて説明していきます。
2.結論
先に結論から述べると、LEDは白熱電球に比べて非常に高効率且つ長寿命です。
エネルギーの変換効率が良く、損失が少なく、壊れにくいということです。
なぜそうなっているかは白熱電球の発光原理を知る必要があるので、そちらの説明をしていきます。
3.発光原理と性能の比較
白熱電球は以下のような見た目をしています。

白熱電球の発光原理は単純で、フィラメントという細い金属線(コイル状にぐるぐる巻きされている場合もある)に電流を流すことで光を発生させています。
下部の電極から電源を供給して、フィラメントに電流を流しています。
フィラメントに電流を流すと温度が上昇し、2000℃以上もの高温になります。
温度が2000℃を超えると何が起こるのかというと、橙色に光ります。
なので、光を生み出す為に電流を流しているというより、電流を流して高温にすることで副次的に光を得ているのが白熱電球なのです。
その為、電気エネルギーの大半が熱エネルギーに変換されていて、光エネルギーへの変換効率は悪いです。
2000℃なんて高熱を発生させているのですから当然ですよね。
また、フィラメントは消耗品なので使用に伴い徐々に蒸発していき、最後には切れてしまいます。
なので、お世辞にも長寿命とは言えません。
それに対して、LEDは最初に述べた通りあくまで余剰に発生したエネルギーを利用して発光させているので余分な損失が少なく、変換効率が良好です。
電気エネルギーを直接光エネルギーに変換しているので、白熱電球のように熱くなることはありません。
また、フィラメントのような消耗品を使用しないので寿命も長いですし、サイズもコンパクトになっています。
赤外線・紫外線をあまり含まないので光による物質へのダメージも少ないですし、水銀や鉛などの環境負荷物質も使用していないです。
ついでに言うと、白熱電球の1/6~1/10の電力で同等の明るさを得られると言われています。
つまり、性能が完全に白熱電球の上位互換になっているわけです。
だから積極的にLEDを採用する流れになっているのです。
デメリットを述べると、白熱電球と比較するとLEDの方がコストはかかってしまいます。
ですが、その分長寿命でメンテナンスが不要になると考えるとやはりLEDの方が都合が良いのでしょう。
ちなみに、フィラメントは電気の世界では細い金属線を指していますが、本来は長繊維のことを指しています。
そもそも、電球は1878年にエジソンが発明したのですが、初期のエジソン電球と呼ばれる電球は本来の意味でのフィラメントを使用していました。
木綿糸(繊維)にすすとタールを塗って炭素化させたフィラメントを用いていたんです。
このフィラメントでは数十時間の点灯が限界でしたが、京都にある竹を使ったフィラメントで1000時間以上点灯させるのに成功し、10年近くはその電球が使用されていたようです。
今では普通に金属を使うようになっていますけどね。
色々な試行錯誤の上にできたのが今の金属製のフィラメントなのです。
※ 金属製フィラメントはタングステンを使うのが主流です。
以上、「LEDと白熱電球の違い」についての説明でした。