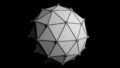今回は、「FCC認証」について記述していきます。
目次
1.規格と法律の違い
本題に入る前に規格と法律について補足説明します。
まずは規格からです。
単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。
イマイチわかりづらい説明ですよね。
なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください。
例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。
その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。
売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。
大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。
なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です。
この指示が規格というイメージです。
こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。
ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。
ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。
次は法律についてです。
規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?
規格は標準・基準を表すものでした。
規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。
あくまで任意です。
その点、法律は守らないと罰則があります。
ここが大きな違いです。
そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。
内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。
専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。
2.FCC認証とは?
FCC認証とは、北米(アメリカとカナダ)向けの電子機器(無線機器や情報技術装置)への認証制度のことです。
要するに、『北米で電子機器を販売するにはこのFCC認証を取得してくださいね』ということです。
FCC[Federal Communication Commission(連邦通信委員会)]というアメリカの機関が制定しているので、そのままFCC認証と呼ばれています。
FCCとは、通信法によって1934年に設立された民間電気通信産業分野に対して規制を制定している独立機関です。
米国市場に出荷される電子機器に対して通信・電波に関わる様々な規制を設けることで、無線機器による通信サービスを円滑に行えるようにしています。
例えば、通信に使用する周波数帯の割り当てを指定したりなんかしています。
他には、EMI規格・試験方法・輸入ルールなども定めています。
その為、北米向けに電子機器を販売しようと考えた場合、EMI試験時にこのFCC認証が登場します。
EMCではなくEMIと書いてあることからわかる通り、FCC認証は「対象の電波が他の電子機器に影響を与えないこと」を証明するものです。
なので、後述するFCC認証を証明するマークやラベルが貼り付けてあったとしても、それは電子機器の電波放射の程度について保証するものであって、製品自体の品質や安全性を保証するようなものではないという点には注意が必要です。
3.FCC認証を行う機関(TCBについて)
FCC認証はFCCという機関が制定しているわけですが、FCC認証の試験を行っているのはFCCというわけではありません。
昔はFCCがFCC認証試験を行っていたのですが、近年はFCCに代わってTCBがFCC認証試験を行うようになっています。
TCBとは、[Telecommunication Certification Body]の略称です。
直訳すると[電気通信事業者認定機関]となり、その名から想像できる通りFCCからFCC認証を行うことを認められた試験機関を指しています。
ちゃんと『この機関なら滞りなく認証試験を実施してくれますよ』という本家本元のお墨付きの機関が存在するのです。
4.FCC認証をする2つの方法
FCC認証はTCBに依頼して実施するわけですが、実はもう1つ方法が存在します。
それは、自分での認証試験です。
自分たちでFCC認証に相当する試験を実施するのです。
ただ、自分での認証はある条件を満たしている機器にしか適用できません。
その条件とは、「意図的・故意に電波を放射しない機器」です。
要は、使用目的が電波を飛ばすことである無線機器なんかは、TCBでの認証が必須になるのです。
電波を使用する機器に関しては、しっかりとFCCに認定された専門の機関であるTCBが試験を行い、より正確な試験・評価を行えるようにしているという話です。
「意図的・故意に電波を放射しない機器」に対して事業者が自分で認証試験を実施する場合、SDoC(供給者適合宣言)を作成する必要があります。
このSDoCを作成すれば、FCC認証まで取得する必要はありません。
ただ、“自分で”確認した上で“自分で”問題無いと太鼓判を押すわけですので、SDoCを作成する場合も結局はしっかりとEMI試験をやる必要があります。
それでEMIに問題があったら自分の責任になりますからね。
「意図的・故意に電波を放射しない機器」としては、以下のような製品が該当します。
- コンピュータ
- TVのインターフェース機器
また、例外として、以下のような許可された周波数帯で運用する機器の場合も「意図的・故意に電波を放射しない機器」という扱いになります。
- コードレス電話
- 無線LAN
「意図的・故意に電波を放射する機器」の場合、事業者が申請書・試験データ・回路図などの必要書類をTCBに提出し、TCBが証明書・認証書をFCCに提出するという流れになります。
試験自体もTCBに依頼することができるとは思うのですが、私自身がやったことないのでイマイチわかっていません。
ちなみに、事業者が提供した製品情報はFCCのデータベースで公開されます。
5.マークとラベル表示
FCC認証の取得またはSDoCの作成をした製品は、それら証明するためのマーク・ラベル表示が義務付けられています。
表示するのは、以下の3点です。
①FFCマーク(ロゴ)
②FCC IDが付いたFFC識別子ラベル
③認証を受けた規則を示す事項
場合によってどれを表示するのかは変わってきます。
①FFCマーク(ロゴ)
JIS規格の〄みたいなヤツです。
(※環境依存文字でJISマークが出てくることを今回知りました。)
普通に検索すればどんな見た目なのかはすぐに把握できます。
Cの中に小さくCを描くことで無線を表しているように見えなくもないので、ロゴの中では比較的覚えやすい気がします。
このロゴは、SDoCを採用した場合に必要になります。
このロゴに合わせて、製品識別用の名称とモデル名も表示する必要があります。
②FCC IDが付いたFFC識別子ラベル
製品を識別するためのコードを示したラベルです。
FCC IDという名称で、FCC IDの構成は「FCC ID:xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx」のようになります。
3文字~5文字の申請者コードにハイフンが付き、その後ろに申請者が指定したモデルを表すコード(数字・英大文字などで最大14文字で設定)が続きます。
このラベルは、FCC認証を受けた場合に必要になります。
③認証を受けた規則を示す事項
以下の文を製品の見やすい場所に表示する必要があります。
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
訳:
このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は次の2つの条件に従う:(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはならない、(2)このデバイスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受け取ったすべての干渉を受け入れなければならない。
この内容を読んでわかる通り、「FCC part 15」というものに該当する場合はこの文の表示が必須になります。
「FCC part 15」とは、無線デバイスに関する規則が定められています。
この規則内に記載されている内容の一部がこの文面だったりします。
この文は結構な長さになりますので、対象機器が小さいとどうやっても表示できるものではありません。
その場合は、取扱説明書に記載することが許可されています。
ちなみに、「FCC part 15」の他には「FCC part 2」というものが存在し、こちらは一般規則について定められています。
FCC認証を取得している製品なのか、SDoCを作成した製品なのか、見分けがつくようになっているわけですね。
以上、「FCC認証」についてでした。