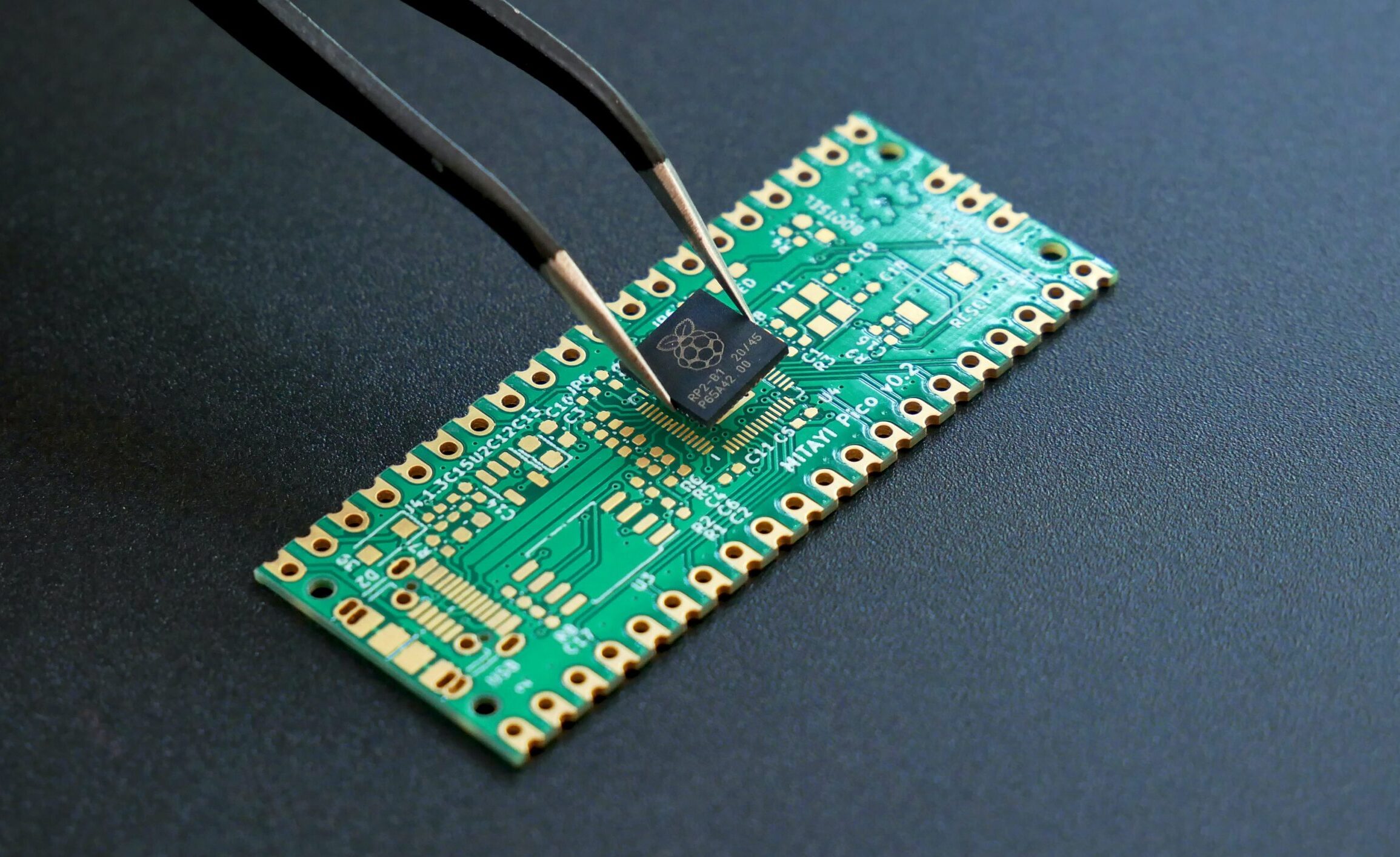今回は、「インピーダンスコントロール」についての説明です。
目次
1.特性インピーダンスとインピーダンスコントロール
特性インピーダンスという用語があります。
説明すると長くなるので、詳しく知りたい場合は以下の記事を参照してください。

ここで理解しておいて欲しいのは、プリント基板内の回路やケーブルなどの伝送路には特性インピーダンスというパラメータが存在し、このパラメータを合わせていないと何かと不都合があるということです。
基板のパターンにも特性インピーダンスが存在します。
なので、場合によっては特性インピーダンスの整合性を取るために、基板のパターンの特性インピーダンスが一定の値になるように作り込む必要があったりします。
このことをインピーダンスコントロールと呼びます。
プリント基板を製作依頼をする際、基板のサイズ・厚さ・材質など、諸々を指定する必要があります。
この時にパターンを指定してインピーダンスコントロールをしてもらうことが可能です。
逆に言うと、指定しなければインピーダンスコントロールはしてくれないので、どこにインピーダンスコントロールが必要かは設計者がしっかりと考える必要があります。
2.プリント基板における特性インピーダンスの作り込み方
プリント基板における特性インピーダンスは、パターン幅・パターンの厚み・クリアランス(基準となるGNDとの距離)・パターンとGNDの間にある誘電体(絶縁体)の比誘電率などを基板製造時に調整することで、作り込むことが可能です。
例えば、以下のように特性インピーダンスは変化します。
- パターン幅を広くして断面積を広げると、その分特性インピーダンスは下がる。
- パターンの厚みを増すと、その分特性インピーダンスは下がる。
- クリアランス(基準となるGNDとの距離)を狭めると、その分特性インピーダンスは下がる。
- パターンとGNDの間にある誘電体(絶縁体)を薄くすると、その分特性インピーダンスは下がる。
- 誘電体の比誘電率を大きくすると、その分特性インピーダンスは下がる。
パターンは導体である銅箔になっているので、軒並み抵抗値を下げる行為が特性インピーダンスの低下に繋がるとイメージしておくと良いかもしれませんね。
こうして調整した特性インピーダンスは、テストクーポン(※)と呼ばれるパターンの特性インピーダンスをTDR測定機という機械で測定して、出来合いを確認しています。
テストクーポンとは、実際にインピーダンスコントロールした配線仕様と同じ(同一配線層・同一配線幅)パターンを基板の不要部分に形成したもののことです。
要するに、インピーダンスコントロールしたパターンの複製を作るわけです。
このテストクーポンは実際にインピーダンスコントロールしたパターンと同等の特性インピーダンスを持っているので、テストクーポンの特性インピーダンスを測定することでインピーダンスコントロールの誤差を確認し、OK/NGの判定をします。
『テストクーポンを形成せずとも実際のパターンの特性インピーダンスを測定すれば良いのでは?』という疑問を持つかもしれませんが、外乱の影響を気にせずに特性インピーダンスを測定するにはテストクーポンを形成するのが確実なんだと思ってください。
ちなみに、インピーダンスコントロールをするということは作業が増えることを意味するので、基板製造コストが増します。
特に、同一基板で異なる特性インピーダンス値で何箇所もインピーダンスコントロールをしたり、層を跨いでインピーダンスコントロールをすると、基板製造難度が上がるので高コストになります。
同一層では同じ特性インピーダンスで統一したり、インピーダンスコントロールが必要な箇所の選定には注意しましょう。
3.どんな場合に特性インピーダンスを一定に作り込む必要があるのか?
“場合によっては”特性インピーダンスが一定の値になるように作り込む必要があると述べましたが、そもそもどんな場合にインピーダンスコントロールが必要になると思いますか?
答えは、シリアル通信などの高周波信号を取り扱う場合です。
特性インピーダンスとは、配線をすると意図していない箇所にコイルやコンデンサが発生したような現象を引き起こすので、その影響を電圧と電流の比で表したものです。
要するに、配線すると所々にコイルやコンデンサの影響が出てくるんですよ。
コイルやコンデンサは、交流を流すと反応する素子ですよね?
コイルは電流変化を妨げますし、コンデンサは充放電を繰り返しますからね。
ということで、信号の周波数が上昇するほど及ぼす影響が大きくなっていくんです。
その為、USBやEthernetなどのシリアル通信の経路にてインピーダンスコントロールを行っていることが多いです。
そもそも、USBケーブルやEthernetケーブル(LANケーブル)はそこを考慮して最初からインピーダンスコントロールがされています。
なので、ケーブルを接続する基板側は、使用するケーブルの特性インピーダンスに合わせてインピーダンスコントロールをする必要があります。
こうすることで信号の劣化や反射を最小限に抑えた状態で通信ができるのです。
4.一般的な特性インピーダンス
基板を構成するパターンがシングルパターンの場合、特性インピーダンスは30Ω~80Ωとされているのが一般的です。
差動信号のような2本でセットになっているパターンの場合、お互いの伝送路の信号が影響し合うため、その状態に応じて特性インピーダンスが異なってきます。
特に差動信号における特性インピーダンスのことを差動インピーダンスと表記していることがあります。
代表的な差動インピーダンスは、以下のように推奨されています。
PCIe(2.5Gbps)…100Ω
PCIe(5Gbps)…85Ω
USB…90Ω
以上、「インピーダンスコントロール」についての説明でした。