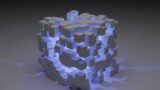今回は、「ノイズの影響とノイズ対策の種類」についての説明です。
1.初めに
別の記事にて、電気設計をする上で気を付ける点として、「ラインレギュレーション(入力電圧の変動に対する出力電圧の変動の割合)」・「部品の個体差によるバラつき」・「熱による影響」などについて説明してきました。
これらの要素以外に、もう1つ注意すべき大事な要素があります。
それがノイズ/雑音です。
今回は、ノイズとはそもそも何なのかという基礎的な部分から、順番にわかりやすく説明していこうと思います。
2.ノイズとは?
ノイズ[noise]とは、必要となるデータから見た不要な要素のことです。
端的に言うと雑音のことです。
電気回路においては、本来の電気信号に意図しない無作為な変動を及ぼす要素と言えます。
例えば、Aさんと仕事の話をしている最中にBさんが『家に居場所が無い』と愚痴ってきたとします。
この場合、Aさんと仕事の話をするのが重要であって、Bさんは邪魔者でしかありません。
つまり、Bさんがノイズに当たります。
お前の家庭事情なんて知るか。そんなんだから居場所が無いんだよ。
こんな関係が通信にも出てきます。
必要なモノだけ受信したいのに、伝わってくる最中に余計なものを拾ってきてしまうのです。
その結果、音声通話に雑音が混じったり、TVやPCの画面に乱れが生じたり、一時的にインターネットの接続が途切れたりするのです。
これらの現象の主原因がノイズというわけです。
ノイズは、自然に発生するものと人工的に発生するものに分類されます。
ここまで説明してきたものは人工的なノイズですね。
人が作った機械類から発生するノイズですから。
そもそも、何かに電流が流れるとノイズが発生します。
導体に電流が流れると、大小の違いはあれど周りに磁界と呼ばれる空間が形成されます。
この磁界内で導体を動かすと、動かした導体に起電力が発生し、電流が流れます。
とにかく、磁界が発生していると周りの導体に意図していない電流が流れやすくなると思ってください。
では、電気信号ってなんでしょうか?
電気の流れ、電流のことですよね?
ということは、電気機器が動作していると、周りに磁界が発生するんですよ。
この磁界に反応して導体に意図しない電流が流れてしまうので、この電流がノイズになっているのです。
これが人工的なノイズの正体です。
では、自然現象として発生するノイズってどんなものだと思いますか?
一番身近な例だと、静電気が挙げられます。
冬場にドアノブに触れた瞬間にバチッとくるアイツです。
製品に触れた際に静電気が発生して内部部品に当たってしまうと、それがノイズになって意図せぬ動きを見せることがあるわけです。
身の回りには様々なノイズが存在するんです。
3.ノイズの影響を測る試験について
身の回りにはノイズが飛び交っていることはわかりましたが、そのノイズを取り込んだ電気製品が一々誤動作を引き起こしていたら製品として成り立ちませんよね?
なので、電気製品は売りに出す前にしっかりとノイズに関する試験を行っています。
製品がどの程度ノイズを発するのか、ノイズを受けた時にどの程度のレベルなら誤動作を引き起こさないかなどを、事前に調べて改善しているんです。
そのレベルが一定水準に収まって初めて製品として売りに出されます。
この試験方法やクリアレベルは世界的な規格で定められているので、私たちが日常生活を過ごす中でノイズで困ることはほとんどありません。
もし規格で定められていなかったら、電子レンジの発するノイズで洗濯機が止まるとかカオスな状況になっていたかもしれないんですよ。
この辺りは次の記事でもう少し詳しく触れていきます。
4.ノイズ対策の種類
ノイズは様々な経路を経由して伝わってくるものです。
その為、ノイズ対策と言ってもノイズが伝わってくる経路ごとの対策が必要になります。
目的地に向かうまでの移動手段が自転車・バス・タクシー・電車など複数あるのと同じ現象です。
電車を止めたところで、バスやタクシーが動いているなら、目的地には到達できるでしょう?
それと同じで、どこか一箇所に対策をしても、他の経路から伝わってくるかもしれないんですよ。
ノイズは様々な経路を経由すると述べましたが、大きく分類すれば空間を伝わってくるか機器の間にある導体(電線など)を伝わってくるかの2パターンしか伝達経路はありません。
この2パターンの伝達経路には、それぞれシールドとフィルタという代表的な対策が存在します。
対象物を金属で覆うことで周囲の空間からのノイズと対象物が発するノイズを遮断すること。
対象物の周囲にノイズに対する盾[shield]となる処理をしているということですね。
電波暗室やシールドケーブルなどがシールド処理を行っている例となります。
EMC試験を行うために部屋内外を遮断した特殊な部屋が電波暗室(シールドルーム)、電線を覆うようにシールド処理を施したケーブルがシールドケーブルです。
原理としては、保護したい対象物よりも導電性の高い導体(ノイズ/電気信号を通しやすい金属)で覆って、その導体をGNDに落としているだけです。
導体で覆っているので内外からやってくるノイズは導体に吸収され、導体を伝ってより電気の流れやすいGNDに向けてノイズが逃げていくのです。
ちなみに、シールドの材質・厚みや密閉具合によってシールド効果は左右されます。
ノイズを逃がすための媒体が変わるわけですので、当然ですね。
その為、対象物を囲う際にスリット(隙間)を用意すると、シールド効果に大きく影響してきます。
対象物の放熱性の問題でどうしてもスリットが必要な場合もありますので、注意が必要です。
スリットを用意する際は、スリットの面積ではなく最大長を抑えることを意識するのが一般的に良いと言われています。
パソコン・テレビなどの排熱機構をイメージしてください。
小さい穴が多数空いていませんか?
あんな感じのスリットが排熱しつつノイズ対策するのに向いているのです。
ただし、ノイズの種類によっては必ずしもそうとは限らないので、過信しないでください。
このシールドとフィルタを併用することで、ノイズ対策を行うのです。
何故片方ではダメなのかはよく考えればわかります。
導体って電気を流しますよね?
ということは、電子機器だけではなく導体部分も空間からのノイズを受け取るんです。
逆もまた然りで、導体部分から空間に向けてノイズを放射もしてしまうんですね。
なので、どちらか片方だけ対策しても、結局もう片方の経路からノイズが出入りしてしまうわけです。
5.ノイズが問題視されるようになった背景
今となっては当たり前のように試験・検証するようになっているノイズですが、昔はそんなに気にされていませんでした。
技術革新の過程で新たなノイズが発生するようになり、対策をしていく必要が出てきた…という経緯になります。
ノイズが問題視されるようになってきた主な原因としては、デジタル機器の普及・小型化・高周波の利用などが挙げられます。
そう言われてもイメージしづらいかと思いますので、例をいくつか挙げていきますね。
現代社会では仕事をしている人の大半がパソコンを使用しているはずです。
業務に限らず、メール・勤怠管理などでもパソコンを触る機会がありますからね。
そんなパソコンですが、当然ながら白黒テレビやラジオが普及していた時代には存在していません。
なので、昔は現代と比べると周りを飛び交っている電波が非常に少なかったんです。
そこにパソコンが普及し出して電波の飛び交う量が増えたことで、テレビやラジオの通信に影響を与え、ノイズが増えていきました。
今は小中学生でもスマートフォンを持っている時代ですが、昔はガラケーなんてものが存在しました。
折り畳みができたり、ボタンが付いてたりするヤツです。
営業の方ならたまに会社支給で持っている人はいますね。
携帯電話が普及して一般人の連絡手段の幅が広がったのは非常に良いことなのですが、浮き彫りになった大きな問題があります。
電車の中に優先席ってありますよね?
優先席の説明で、「優先席付近では、携帯電話の電源を切ってください」という文面を見たり、アナウンスを聞いたことがありませんか?
あの注意をしている理由の1つとして、ペースメーカーの誤作動が挙げられます。
ペースメーカーとは、心臓に疾患を抱えている方が心臓に電気刺激を与えることで人工的に心臓を動かす装置のことです。
心臓が悪い人が補助用に付けている装置だと思ってください。
このペースメーカーの動作に携帯電話の電波が干渉して、ノイズになったのです。
このように、携帯電話の電波がノイズとなり、医療機器に影響を与えてしまう事例はいくつかあったようです。
今でも携帯(スマートフォン)の電源を切るように促されている気がするので、いくら対策をしても精密動作が必要な医療機器にとってはノイズになることには変わりは無いのでしょうね。
他にも、カードリーダーが静電気の影響でまともに機能しなくなるだとか、携帯電話の電波が脳腫瘍の発生や発がんに起因しているだとか、Wi-Fiなどの電波で頭痛・疲労感を引き起こして最悪は自殺するだとか、社会現象になっている事例は結構あります。
だからこそ、EMC対策に焦点が当てられるようになっているのです。
以上、「ノイズの影響とノイズ対策の種類」についての説明でした。